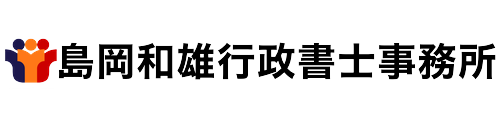貨物軽自動車運送事業 令和7年4月1日からの変革!!

貨物軽自動車運送事業者が令和7年4月1日から新たにやらなくてはいけないことが増えました。
それはどういうものなのか、今回はそこをテーマについてお話ししていきたいと思います。
目次
貨物軽自動車運送事業者 R7年4月1日から何をしなくてはいけないのか?
| 法令で定められている事項 | 概要 | 実施タイミング |
|---|---|---|
| 貨物軽自動車安全管理者の講習受講 | ・貨物軽自動車 安全管理者は選任前に加えて、選任後も2年ごとに受講しなければいけません。 | |
| 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出 | 営業所ごとに選任し、選任時には法令で定められた事項について、運輸支局等に通じて国土交通大臣に届出しなければいけません。 | |
| 初任運転者等への指導及び適性診断の受診 | 法令で定められた初任運転者等の特定運転者にたいして、特別な指導をしなければなりません。また、適正診断を受診させなければなりません。 | |
| 健康状態の把握 | 運転者に対して、雇い入れる際や、1年に1回健康診断を受診させ、受診結果を事業者に提出させなければいけません。 | |
| 運転者に対する指導及び監督 | 運転者に対して、運行の安全確保のために必要な運転技術や関係法令の遵守事項の指導・監督を毎年実施しなければいけません。 | |
| 点呼 | 運転者に対して、乗務の前後に必要事項を確認し、運行の安全を確保するために必要な支持をしなければいけません。 | 乗務前・乗務後 |
| 運転者の意勤務時間の遵守 | 運転者の勤務時間は、法令で定められた時間の範囲内に収めなければいけません。 | 乗務前・乗務中・乗務後 |
| 異常気象時における措置 | 台風接近時に必要に応じて運行を中止したり、雪道では冬用タイヤを装着するといった、輸送の安全を確保するための措置を講じなければいけません。 | 乗務前・乗務中 |
| 業務の記録(バイク便を除く) | 法令で定められた項目について記録を作成し、1年間保存しなければいけません。 | 乗務前・乗務後 |
| 過積載の防止 | 過積載による運送を前提とする運行計画の作成や運送の引き受け、支持をしてはいけない | 乗務前 |
| 貨物の適正な積載 | ・貨物の重さが前後や左右で偏らないようにしなければいけません。 ・にくずれして貨物が落下しないよう、ロープやシートをかけなければいけません。 | 乗務前・乗務中 |
| 事故の記録 | 事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等を記録し、3年間保存しなければいけません。 | 乗務後 |
| 国土交通大臣への事故報告 | 死傷者を生じた事故等について、運輸支局などを通じて国土交通大臣への報告をしなくてはいけません | 乗務後 |
と、このような感じなります。
ここからは細かく見ていきましょう
新・貨物軽自動車安全管理者の講習受講
貨物軽自動車運送事業者は、貨物自動車安全管理者に選任しようとしているものに貨物自動車安全管理者講習を、貨物軽自動車安全管理者の貨物軽自動車安全管理者定期講習を、国土交通大臣の登録を受けた講習機関で受講させなければいけません。
- 貨物軽自動車安全管理者講習:貨物刑事自動車安全管理者の選任にあたり受講する必要あり
- 貨物軽自動車安全管理者定期講習:選任後2年ごとに受講
新・貨物軽自動車安全管理者に選任・届出
貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任しなければいけません。
なお、「貨物軽自動車安全管理者」を選任したときは、管轄の運輸支局に届出をしなければいけません。
- 貨物軽自動車運送事業者の氏名及び名称
- 貨物軽自動車安全管理者の氏名及び生年月日
- 貨物軽自動車安全管理者の選任年月日及び講習修了年月日
新・初任者運転者等への指導及び適正診断の受診
貨物軽自動車運送事業者は、以下の運転者に対して特別な指導をしなければいけません。
また、国土交通大臣に認定された適正診断の受診もさせなければいけません。
- 初任運転者(過去に一度も特別な指導・適性診断を受けていない者)
- 高齢者(65歳以上の者)
- 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者(事故惹起者)
また、貨物軽自動車運送事業者は運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の状況などを記載した貨物軽自動車運転台帳を作成し、これを営業所に備えおかなければなりません。
新・業務の記録
貨物軽自動車運送事業者は、行った業務について主に移管も項目等の記録を作成し、1年間保存しなければいけません。
- 運転者等の氏名
- 車両番号(ナンバープレート等)
- 業務の開始、終了及び休息の日時
- 業務の開始、終了及び休息の地点
- 業務に従事した距離
- 主な経過地点
新・事故の記録
貨物軽自動車運送事業者は、事故が発生した場合、主に以下の項目等の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
- 乗務員等の氏名
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 事故の概要
- 事故の原因
- 再発防止の対策
新・国土交通省への事故報告
貨物軽自動車運送事業者は、死傷者を生じた事故など、重大な事故が発生した場合、主に以下の項目等について、30日以内に所定の様式より運輸支局などを通じて国土交通大臣に報告しなければいけません。
加えて、2人以上の死傷者を生じた事故など、重大な事故については、24時間以内においてできるだけ速やかに運輸支局等に速報しなければなりません。
- 自動車の使用者の氏名又は名称
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 当時の状況
- 当時に処置
- 事故の原因
- 再発防止の対策
引き続き実施が必要な主な安全対策
点呼
乗務前に運転者や事業用自動車に何らか問題が確認された場合は、運行してはいけません。
また、点呼の内容は日々点呼記録簿に記録したうえで1年間保存しなければいけません。
(1)運転者の酒気帯びの有無:乗務前・乗務後
アルコール検知器を用いて、酒気帯びの有無を確認するとともに運転者の状態を目視で確認します。
※一人で事業を行っている場合は、自ら確認を行ってください。加えて、ご家族と同居している場合には自信の体調を客観的に見てもらうことも有効です。
(2)運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無:
乗務前
体温や血圧、顔色、呼気の臭い、声の調子の情報によって、確認します。
(3)業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況:乗務後
気になる点がなかったかを確認します。
(4)車両の日常点検の実施又はその確認:乗務前
走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期にエンジンルーム内、ライト、タイヤ、運転席周りについて、目視などにより確認します。
運転者の勤務時間の遵守
安全な運行のために以下の内容を守り、運転者に休息を十分に与えましょう。
| 1年、1か月の拘束時間 | 1年:3300時間以内 1か月:284時間以内 |
| 1日の拘束時間 | 13時間以内 (上限15時間、14時間超は週2回までが目安) |
| 1日の休息時間 | 連続11時間以上を与えるように努めることを基本とし、9時間を下回らない |
| 運転時間 | 2日平均1日:9時間以内 2週平均1週:44時間以内 |
| 連続運転時間 | 4時間以内 |
運転者に対する指導及び監督
運転者に対する指導及び監督を毎年実施する必要があります。
- 実施した日時と場所
- 実施内容
- 実施した者と受けた者
を記録したうえで3年間保存しなければなりません。
まとめ
とこのようなことがR7年4月1日から行わなくてはならない項目になります。
貨物軽自動車運送事業も一般貨物自動車運送事業と同じことをしなくてはいけなくなったということですね。
となるともしかしたら、今後は貨物軽自動車も巡回指導などが行われるのかも??
軽貨物の経営届出、安全管理者の選任届、料金届など、全てを行うことができます。
お困りごとがありましたら、弊所までご連絡ください!!まずはお問い合わせを!!