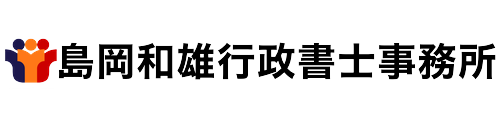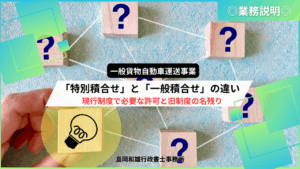「貨物自動車利用運送」と「第一種利用運送」違いを徹底解説

物流業界において“利用運送”という言葉はよく用いられますが、その中身まで正確に理解しているケースは多くありません。特に、「貨物自動車利用運送」と「第一種利用運送」の違いは制度上大きく異なり、誤った理解のまま業務を進めると、結果的に法令違反につながる可能性があります。
本記事では、両制度の法的根拠から実務上の運用、丸投げ可否、元請責任の範囲に至るまで、専門家の立場から分かりやすく整理します。自社の業務がどちらの類型に該当するのか、また社内でどのように取り扱うべきかの判断材料としてご活用ください。
1.法律上の位置づけの違い
まず最も重要な点は、両制度が根拠とする法律そのものが異なっていることです。ここを理解していないと、制度の意図や義務、禁止行為が混乱しやすくなります。
● 貨物自動車利用運送
貨物自動車利用運送は、貨物自動車運送事業法 第2条7項に基づく制度です。もともとは一般貨物自動車運送事業者が自社の輸送を中心に、補完的に協力会社を使用するための制度として整備されたもので、いわば「自社運行+協力会社便」という運行形態を法律上明確に位置づけたものです。
このため制度の根底には、
“自社が運送主体である”
という前提があります。
● 第一種利用運送
一方、第一種利用運送は、貨物利用運送事業法に基づく制度です。こちらは、自社ではトラックを保有せず、他社の輸送力を活用して荷主と契約を締結する「純粋な利用運送」。純粋な3PL事業者や取扱事業者がこちらに該当します。
制度の中心は、
“自社は運ばず、他社の運送を利用して荷主と契約する”
という考え方です。
つまり、両制度は同じ「利用運送」という言葉が使われていても、制度の出発点から役割まで大きく異なっています。
2.事業の本質
次に、両制度の事業構造の違いを見ていきます。
● 貨物自動車利用運送
この制度は、自社トラックによる実運送が基本です。繁忙時や特定区間のみ他社のトラックを利用するなど、協力会社を併用し柔軟に輸送体制を組む現場で、自然と発生していた運用を制度として位置づけたものといえます。
そのため、
“自社運行が主、外注は従”
という関係性が基本になります。
● 第一種利用運送
こちらは、自社で輸送を行わず全て他社へ委託することを前提とする事業です。荷主との契約、運送の管理、輸送品質の担保など、元請としての機能を担うことが中心的役割になります。
いわば、
“管理者としての元請”
という形態です。
3.外注(丸投げ)の可否
もっとも誤解されやすいポイントです。
● 貨物自動車利用運送の丸投げ(外注100%)
法律上、丸投げは不可です。
貨物自動車利用運送は、自社運送が制度の根幹を形成するため、他社にすべてを委託してしまう運送形態は認められていません。
俗にいう「利用の利用」禁止というルールです。
これは平成15年の制度改正時に明確化されたもので、現在でも厳格に運用されています。
● 第一種利用運送の丸投げ
こちらは反対に、
外注100%で構いません。
むしろ自社で運送を行わないことが前提の制度であるため、丸投げ自体が事業そのものです。
ここを混同してしまうと、法令遵守上の重大な問題が生じます。
4.元請責任(貨物事故時の責任範囲)
貨物事故が発生した場合、誰が荷主に対して責任を負うのか、という問題も制度により異なります。
● 貨物自動車利用運送
元請責任はあくまで自社が実施する輸送が中心にあります。協力会社便を使用する場合でも、自社が管理主体であることを前提に、事故発生時の責任が発生します。
ただし、外注100%の運行は不可のため、丸投げと元請責任の関係が問題になる状況は法律上想定されていません。
● 第一種利用運送
貨物利用運送事業法に基づき、
荷主に対してはすべて元請責任を負います。
事故が発生した場合、元請である利用運送事業者が荷主への賠償責任を負い、その後、実運送会社へ求償する構造になります。この構造こそが第一種利用運送の事業モデルです。
5.実運送の要否
ここも制度を理解する上で非常に重要なポイントです。
● 貨物自動車利用運送
自社による運送が必須です。
協力会社の利用はあくまで補完であり、それのみで事業を成立させることはできません。
● 第一種利用運送
逆に、自社で運送する必要はなく、トラックを持たずとも事業が成立します。
6.制度成立の背景
なぜこのように制度が二つに分かれているのか。歴史的背景を少し整理します。
● 貨物自動車利用運送
平成15年の制度改正までは、利用運送の規制が曖昧で、実運送事業者が外注100%で事業を続けてしまうケースも少なくありませんでした。しかし、荷主保護や輸送品質確保の観点から、
「利用の利用」禁止が明記され、自社運送を基本とした形に制度化されました。
● 第一種利用運送
こちらは昭和期から存在する制度で、物流取扱事業者が荷主と運送契約を締結し、他社の輸送力を使って運送を実現する仕組みとして発展してきました。大手物流企業や3PL企業が採用している形態です。
7.実務イメージの違い
最後に、実務の現場から見た違いを簡潔にまとめます。
● 貨物自動車利用運送
- 自社便を中心とした運行
- 繁忙期や特定区間のみ協力会社を活用
- 外注のみの運行は不可
- 実運送が会社の基盤
● 第一種利用運送
- 自社では運ばない
- すべて外部の運送会社を利用
- 荷主との契約は元請として締結
- 事故時の責任は元請が負う
まとめ
同じ「利用運送」という言葉であっても、
貨物自動車利用運送(ぶら下がり利用運送) と
第一種利用運送(純粋利用運送) では、
法制度、運用、禁止行為、責任構造の全てが大きく異なります。
特に、
- 丸投げの可否
- 元請責任の範囲
- 自社運送の要否
は、事業の適法性に直結するため、正確な理解が不可欠です。
自社の事業がどちらに該当するのか、日々の業務が制度に沿った運用になっているのか、改めて確認することが法令遵守とリスク管理につながります。
本記事が事業者様の理解の一助となれば幸いです。